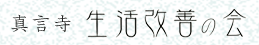生命の祈りについて
少し前のことになりますが、2007年12月東京行飛行機の中の機内誌に「400年前の手紙」という文章が載っていました。オスマントルコの建築家の話でした。
その話は、だいたい次のようなものでした。
1990年代にトルコのイスタンブールでモスクの修復プロジェクトが持ち上がった。難しい修復で何とか木枠を組んでアーチを支えているキーストーンを除去とした時、そこにガラス管に入れられたオスマン語の手紙があった。その手紙には、{この建築物の石は、400年が寿命である。400年後、石のアーチ部分は傷んでもろくなり、あなた方はそこを造り直そうとするだろう。その時、おそらく建築の技術は我々の時代より大きく進化しており、それゆえにあなた方は、石のアーチを造りなおす経験をもっていないだろう。だから、私はこの手紙を書いている。・・・・・・あなた方は石のアーチ部分の重要なキーストーンの下に木の枠組みを設置し、その後キーストーンを除去しようとするだろう。そのプロセスに取り掛かることは、大変重要な意味をもっているキーストーンについて学び始めることを意味している。・・・・・・同封の資料で、あなた方はこの石の建築の総てを学ぶことができるだろう。}というものだった。
この話を読んで、この建築家ミマール・シナンの洞察力に深く敬意を表すると同時に、彼の生きた同じ時代に深く思いを馳せたのでした。
そのころイタリアではドーム型のキリスト教教会を設計したミケランジェロやブルネレスキが活躍しており、ルネッサンスへの転換期でした。
そのとき私は、シナンもミケランジェロもブルネレスキも、その感性と祈りをドームやアーチに表現していたのだと感動したのでした。この時代の造形や芸術は「生命への賛歌-生命の祈り」だと思っています。
この時代の芸術や建築は人類の同じ祈りを表現していると感じるのです。400年経った今でも、まだ「失われた同じもの」を別の表現にしようと努力し続けている現代があると私は考えています。
地球の同じ空気を呼吸して生きている人々の祈りは、同じものに行き当たってしまったのだと捉えているのです。キリスト教もイスラム教も仏教も同じだと思っています。何故なら世界宗教は皆同じ「無形の 絶対なるもの」を祈っているからです。人類が祈っているのは、「皆同じ力の無形のもの」であると 私は感じています。宗教に二つの分け方があります。創造主を認め、唯一絶対の神の愛を説くものと、創造主を認めないもの、この二つです。しかし深い祈りに入っていくと、この区別は、時代と場所と民族の歴史の差であろうと感じられるのです。そして地球という有機的な生命体は、いまだに失ったものを取り戻すために努力し続けていると感じているのです。
失った祈りでもあり、時代の新しい感性でもある、「それ」を表現するために、近代は造形・芸術という手段を人々はとってきています。それは人間の感性に直接働きかけるからだと思います。
そこで私は上野の西洋美術館で三月八日から開かれていた「ウルビーノのヴィーナス」展について、感じたことを書かせて頂くことにしました。「ウルビーノのヴィーナス-古代からルネサンス、美の女神の系譜」というテーマでした。現代に女神の展覧会とは、なかなか「やるな」と思いながら、期待を持って入場したのでした。しかし期待したものとは全く別のものを学んで、展覧会を後にしました。確かにティツィアーノのこの作品は、世界の女性の美の原型になっていたのだと本当に確信してしまったのです。
展示されたものは どれも大変すばらしかったのです。だから尚更はっきりとルネサンスに動いた「命の祈り」は、みごとに「グラビア・アイドル」となっていたことをこの展覧会から学びました。しかし勿論アントロポモルフィクな調和を否定している訳ではありませんし、マニエリスムであると主張している訳でもありません。
現代女性の「美の原型」は、「生命の祈り」をギリシアの女神像に仮託したけれども、いつの間にか、ヴィーナスとして表現された「裸婦」だけが、現代の美の基準であるとの評価を受け、男性から賛美され、一人歩きしてしまったことを教えていました。
ジョバンニ・ダ・サン・ジョバンニの作品の一点が、庶民の母の姿をしたヴィーナスが息子キューピットの髪に櫛をあてていました。母の側面が 描かれていたのは、この作品だけだったと思います。しかし母になる力そのものの表現は、どこにも無かったのです。ロダンの「裸婦」の表現のほうが、まだ現実の女性の「産む願望」とその力を現していると、考えます。しかし直接的である「性」が主張されるため「聖なるもの」の表現が表されにくいと感じています。この混迷した女性像の中で、現代女性は苦しんでいます。
本当の自分とはどんな姿なのか、美しいとは何なのか、女性自身がわからなくなっているのです。どのように生きるべきか、そしてどのように「美しく」あるべきかが判らなくなっています。女性は肉体が産む力のためだけにこの空間に存在している現実を認知してはいません。総ての感性がそこから発していることも気づきません。男性の感性に合わせることによって、生き抜かなければならないからです。
確かに産むための相手、そのための自由はヴィーナス像に仮託することで、現代与えられました。「パリスの審判のりんご」の話に象徴される寓話通りだと思います。
しかし、産むことが総てである「女性」という肉体存在にとって、男性に裏切られることは、命を傷つけられるに等しく、また「自分の人生は一体何だったのか」と自己否定して泣く女性の何と多いことでしょうか。そして自分自身で自分を痛めてしまうのです。子を産んだ、産まなかったではありません。女性の感性の総てが産むという肉体として出来ているということを確認して生きてこなかったのです。
女性には女性の祈りがあるのです。女性を受け入れた社会的空間と生き様があるのです。それが具現化されていないだけです。女性は人間として平等であり、能力も男性とはあまり変わりません。しかし 決定的に唯一つの違いがあります。産む力そのものを肉体としていることなのです。これは 唯一つの差であり、簡単でありますが、実は全てが男性と違うということを意味しています。女性には女性の感性と祈りがあります。総てを許す能力が女性にはあります。「裁き」とは違う「総ての許し」です。
失われた祈りはその中から生まれてきます。密教の大悲胎蔵生曼荼羅に(胎蔵界曼荼羅)にその力が、描かれています。エロスではありません。泥沼から咲くはすの花のように、象徴的な存在分析とともに描かれているのです。
「大日経疏」第三巻の喩えにもありますし、勿論大日経を無視してお話している訳ではありません。